2023/1/1
今年のお正月は『福山城』と『鞆の浦』と聞いたので、蛇足ながらパンフを作ってみました。
1,ヤンチャ大名、水野勝成
福山城は、近世城郭(大阪城や小倉城のように、天守閣があって大きな石垣がある城)として最後に作られたムチャクチャすごいお城。10万石しか領地がないのに、城は100万石並みの立派さ(今で言えば、年収300万円なのに1億円の新築一戸建てを作るようなもの)。もちろん、いつ敵になるか分からない西日本の大名(島津・加藤・黒田・細川・毛利ら)を、姫路城の手前で防ぐために頑丈に作ったんだけど、最強だったのは、初代城主の水野勝成その人でした。
水野勝成とはどんな人?(福山市のサイトをちょっと手直し)

【水野勝成肖像】
ちなみに水野氏は、徳川家康のお母さんの実家で、一族は大名ばかり。父は徳川四天王の水野忠重で、代々、老中(現在の大臣クラス)として江戸幕府をリードしたエリート一家です。「勝成」は水野家の本家筋の息子でした。
記録から見ると水野勝成は戦国最強の武将の一人といってよく、その強さと異常な性格には驚かされるばかりでした。
現代風に言えば、若いときはヤンキーで暴走族に入り、警察にも捕まって親に勘当されたけれど、三十代からは気の強さを売りにいい仕事をするようになり、何度もクビになりかけながら、最後は社長になって88歳まで生きた人、というところでしょうか。
水野勝成の武勇伝&エピソード
・遠江高天神城攻めで初陣で15も首級を上げる。(16歳)
・武田攻めの後の北条氏との戦いで、二千VS一万の圧倒的多数を撃退。わずかの手勢で奇襲をかけ北条勢を大混乱に、敵首級三百を道に吊るし、敵の士気を完全に削いだ。(19歳)
・小牧長久手の戦いで、結膜炎が痛くて、兜なしでいたところを 父から怒られ、逆ギレして辞表を出して突撃、一番首をあげる。 それ以来家には帰らず、家康のもとで働くようになった(20歳)。
・父の部下に悪行をチクられ切り捨てる。激怒した父からとうとう勘当され、奉公構え(ほうこうがまえ:武士世界への出入り禁止)になる。(21歳)
・15年間放浪の身となる。(21~36歳)
(戦国最強のフリーランス。虚無僧、姫谷焼きの器職人などをしながら、いつも大げんかばかりして、殺した人も数知れず。父や豊臣秀吉から殺し屋が派遣されたという伝説もあります)
・秀吉死後家康の元へ。
武士世界への出入り禁止の身だったが、勝手に門番(足軽の仕 事)などしていたがすぐバレた。(33歳)
・家康が強引に水野親子を仲直りさせる。(36歳)
・和解後まもなくの関ヶ原の戦い直前に、父が石田三成に暗殺さ れ、刈谷3万石を継ぐことになる。(36歳)
・関ケ原の戦いで大垣城を攻め落とす。(36歳)
勝成は従五位下に叙任され、「日向守」の官位を受ける。
・大阪夏の陣では息子と(宮本武蔵が息子を護衛)参戦し、軍の 最高責任者でありながら一番乗り。家康に怒られる。真田幸村を討ち取った三隊の一つ。功績第2に賞される。(51歳)
・ヤンキー上がりなのに、福山では名君になって町作り。(60歳)
・75歳で島原の乱へ息子、孫と三代で参戦 ・88歳で没
城下町の建設では、江戸の神田上水につぐ大規模な上水道を整備し、瀬戸内海から運河を城まで引き入れ、大船団を城下に係留させました。
産業では土地を領民にタダで与え、税金を免除して城下の振興を図り、寛永7年(1630)には全国初ともいわれる藩札を発行しました。
その名君ぶりは、後の福山城主の阿部氏が勝成の悪口を創作宣伝しなければならない程でした。
2.西国最強、福山城!
【福山城の復元イラスト(江戸時代)】
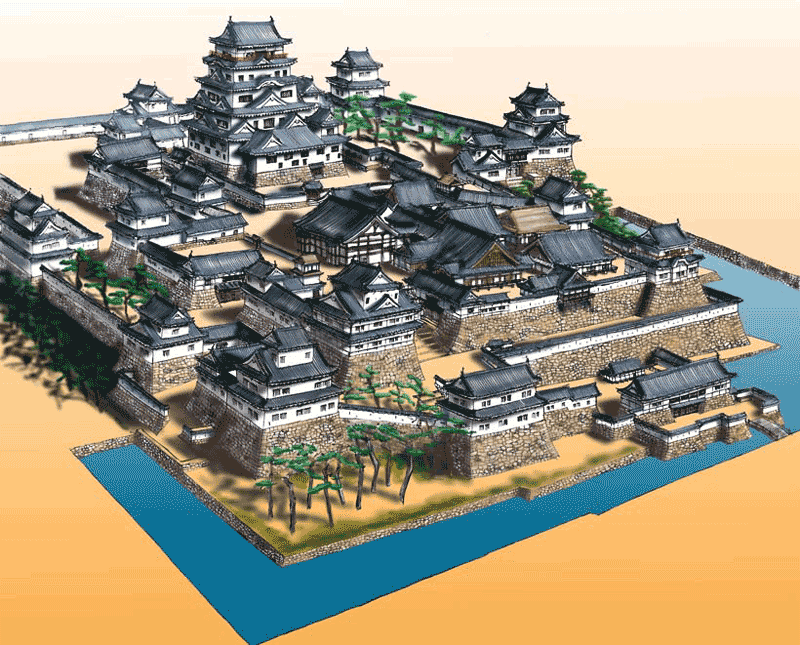
福山城は,徳川幕府の譜代大名であった水野勝成が築いた城で,そのあと、水野家5代・松平家1代・阿部家10代の歴代藩主(みんな幕府の出世コースを歩みます)に受け継がれました。
明治維新後,官軍に負けた福山藩では、天守(てんしゅ),伏見櫓(ふしみやぐら),御湯殿(おゆどの),筋鉄御門(すじがねごもん),鐘櫓(かねやぐら)を除いてほとんどの建物が取り壊され(木材をマキにして売り払いました),二の丸,三の丸は民間に払い下げられ、畑や水田になりました(大名や武士が貧乏になったのでしかたない)。
さらに昭和20年8月の福山空襲により天守と御湯殿が焼けました。
現在の天守,御湯殿,月見櫓(つきみやぐら)は昭和41年に復興されたもので,戦災を免れた伏見櫓,筋鉄御門,鐘櫓とともに福山市のシンボルとして市民に親しまれています。
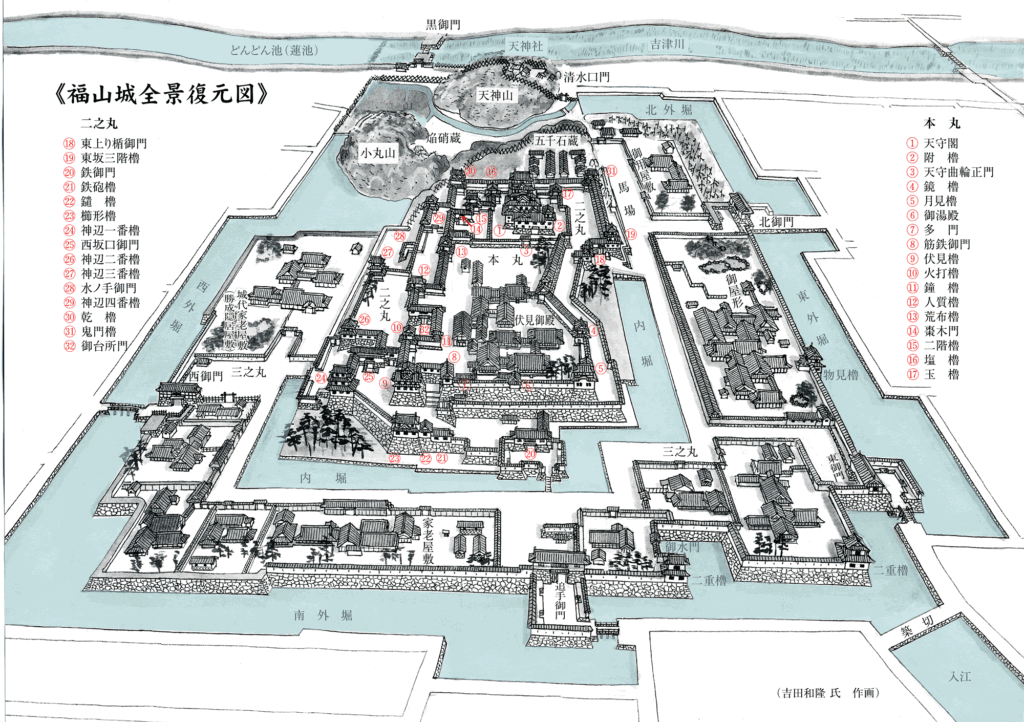
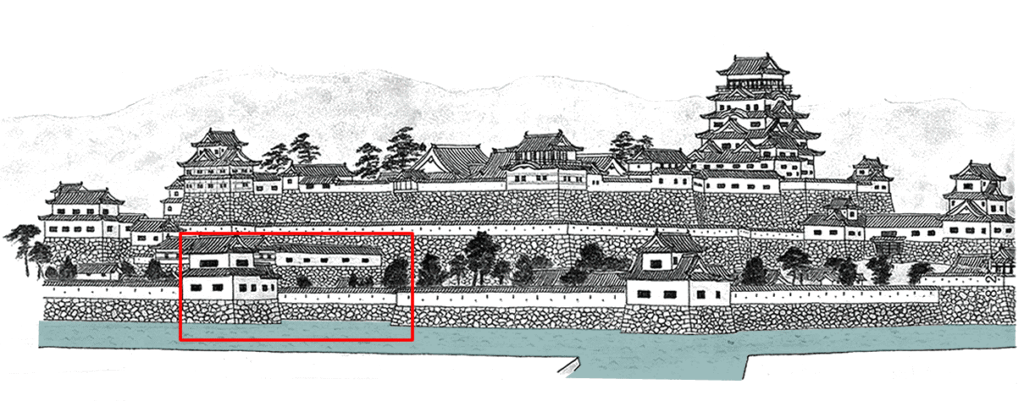
赤枠は舟入。下図は舟入を俯瞰した図および拡大図
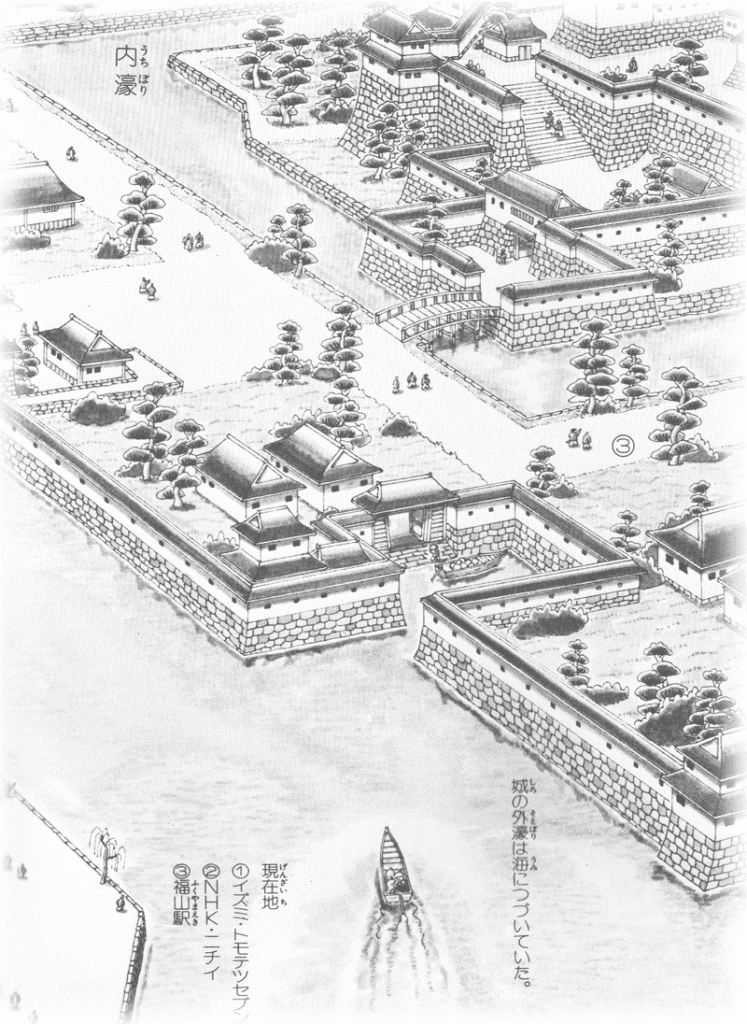
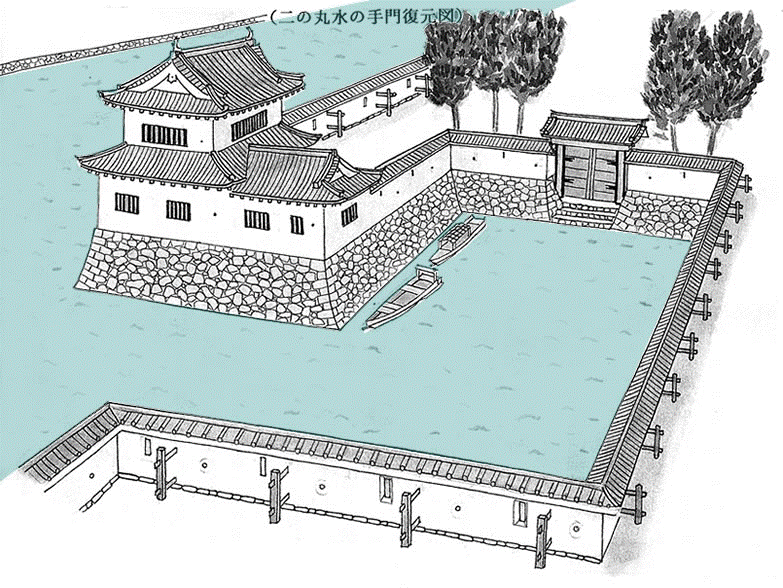
福山城の特徴の一つは、城下町の形成とともに外堀に舟入が設けられ、外堀と福山湾が入川(入江)と呼ばれた運河でつながっていたことです。当時の日本5大名城に数えられるほどの規模で、入り江から船で直接荷を運べる構造でした。
一国一城令の後に築城
水野勝成は、神辺(かんなべ)城に入る予定でしたが、神辺城は海から遠いうえに、過去に何度も落城した黒歴史があったことから、全国的には一国一城令が徹底されていたのに、異例の新規築城を行いました(北九州の黒崎城はこの時に壊されました)。
【江戸初期(水野藩)の城下町地図】
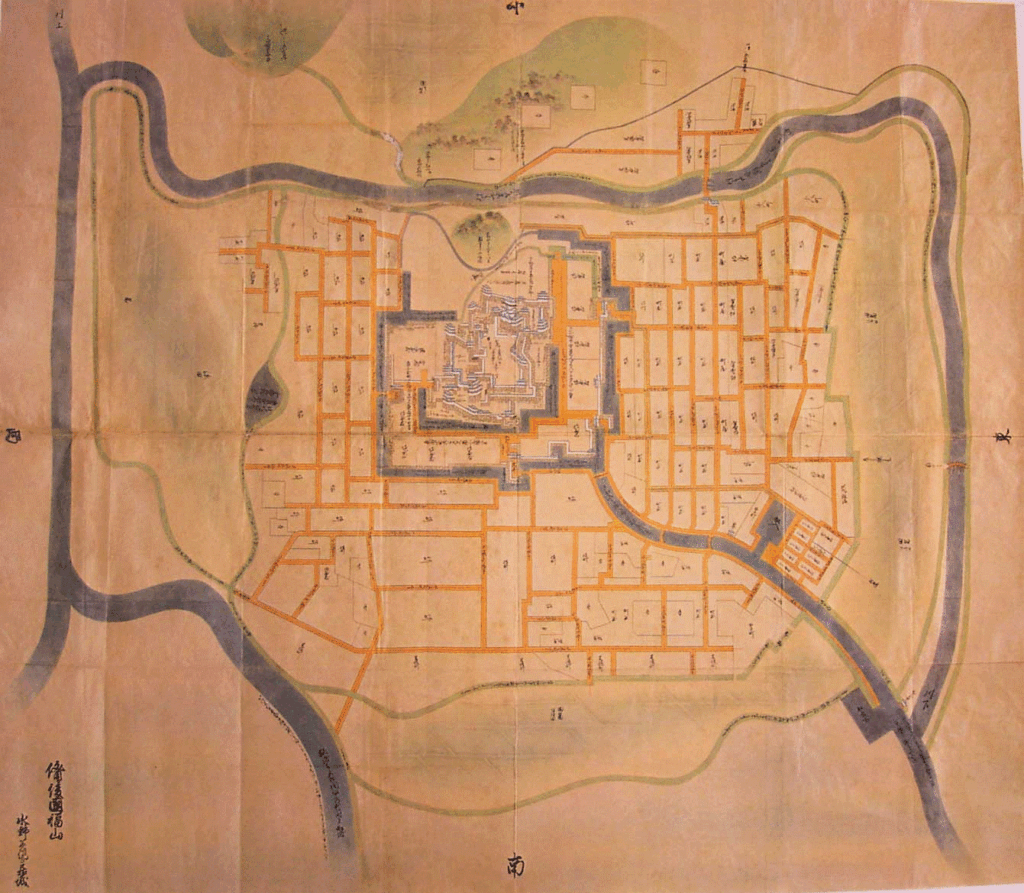
【福山駅前広場の福山城遺構】
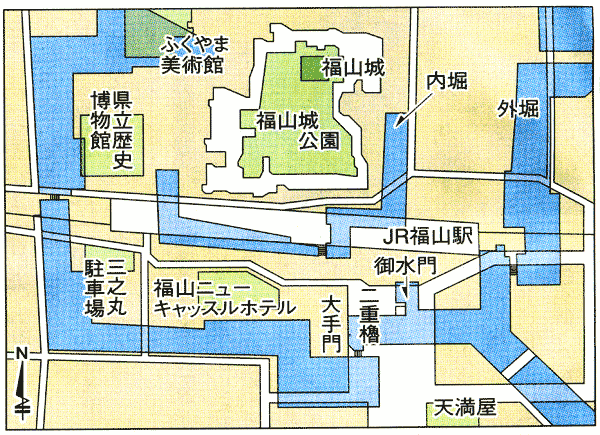
【明治43年の福山市街図】
(米屋町・桶屋町など江戸時代の町名が残る)

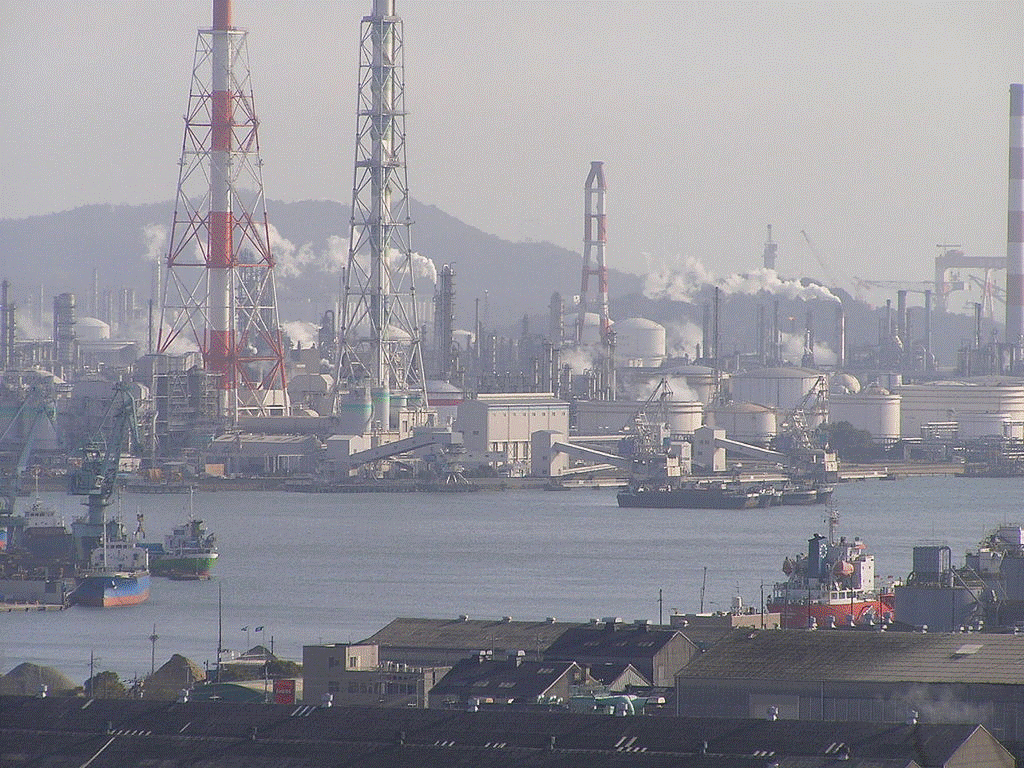
現在の福山市は人口45万人。世界最大級の銑鋼一貫製鉄所(JFEスチール)を抱える重工業都市です。市内に年産1300万トン級の生産能力を持ち粗鋼生産量は日本一です。
(八幡のライバル!)
【福山城はここがすごい】 中国新聞2008年2月5日

3.鞆の浦はなぜ発展したのか
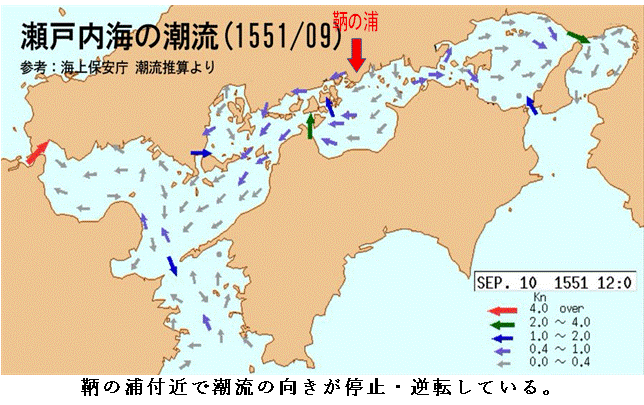
「鞆の浦」は、瀬戸内海のほぼ中央に位置しています。瀬戸内海の海流は、満潮の時は西の豊後水道や南の紀伊水道から流れ込み、瀬戸内海のほぼ中央に位置する鞆の浦沖でぶつかります。逆に干潮の時には、鞆の浦沖を境にして東西に分かれて流れ出していきます。つまり「鞆の浦」を境にして潮の流れが逆転するのです。
エンジン船が発明されるまで、人類は山や木を目印に、潮の流れを利用して船による移動をしていました。帆やオールを使うこともありましたが、それは風や地形など条件がいいときだけで、航海のほとんどは潮まかせです(現在の船でも、潮に乗ると燃費が全然違うので、船長は潮を熟知して運航費を節約しています)。
天候や風向きに恵まれ、瀬戸内海を潮に乗って順調に進んでいた船も、「鞆の浦」では必ずストップしなければなりません。なぜなら、潮が逆向きになって船が進まなくなってしまうからです。しかし、潮流は1日に4回、方向を変えますから、理屈では数時間もすれば進めるはずですが、実際はそんなに簡単ではありません。この頃の船は、暗くなると航海できませんから、日没までに次の港に着かねばならないのです。船頭(船長)さんは、風向きや潮の速さ、船員の体力を計算して出港か潮待ちかを判断します。 荷物や人の運送料金には、潮待ちの時の飲食料も含まれていますから、船員も「できれば泊まりにしてほしい」と思っています。無理に急いで事故を起こしても、損害賠償は船頭さんがしなければなりませんし、船員から嫌われるのも得策ではありませんからのもから、多くの場合、潮待ちに決まったようです。
そうとなれば船員さんは大喜び、なにがしかの小遣いもらって遊びに繰りだします。若い男達の集まりですから、遊びと言えば酒・女・博奕。「板子一枚下は地獄」と明日のことなぞ考えないから金払いはいい。

【鞆の浦の元遊郭街】
「需要あるところ供給あり」の法則で、遊郭・料理屋・賭場(当時はお寺であることが多い)が乱立して「鞆の浦」は瀬戸内最大の繁華街に成長します。
【鞆の浦の寺町】
船頭さんも飲食料(酒手)をもらってますから遊びに行きたかったでしょうが、「船番所」での手続きや「焚場(たでば)」での船の修理の打ち合わせなど結構忙しかったようで、貯めた酒手(さかて)を寺(銀行業もしていた)に預金したりしました。(鞆浦には今でも19のお寺と数十の神社があります)

4.「鞆の浦」に着目した大名たち
これだけの「金のなる木」を政治家(大名)が放っておくはずがなく、湊奉行(みなとぶぎょう)を派遣して入港する船の数をチェックし、運上(表向きは港の人たちから大名への寄付金だが、やがて定期・定額になり、税金化する)を取り立てます。
鞆の浦に注目した有名な大名としては、室町幕府第15代将軍の足利義昭、関ヶ原の戦いで東軍の先鋒として徳川家康の勝利に貢献した福島正則、福山城を築いた水野勝成や後世の福山藩主たちがいます。

【足利義昭像】
足利義昭は、織田信長と対立して京都を追い出され、毛利氏を頼って「鞆の浦」に落ち延びましたが、なお抵抗をあきらめず、「鞆要害(現在の鞆の浦歴史民俗資料館)で全国の大名に信長討伐の手紙を書き続け信長を苦しめました。
近くの常国寺には足利義昭が寄贈した山門(将軍門)や義昭ゆかりの品々が現存しています。
【福島正則像】
福島正則は「賤ヶ岳の七本槍」(しずがだけのしちほんやり)の筆頭として知られる戦国武将です。幼少の頃から小姓として豊臣秀吉に仕え、「豊臣秀吉子飼いの武将」として多くの合戦で活躍し、戦国の世にその名を轟かせました。関ヶ原合戦の戦功として、安芸・備後49万石を与えられましたが、特に「鞆の浦」の価値に着目し、「鞆城」を築いて瀬戸内海の支配を確実にしようとしました。

これが幕府ににらまれて、改易(大名をクビになり領地を没収されること)されました。「鞆城」跡には現在、「鞆の浦歴史民俗資料館」が建てられています。
5.今も残る江戸時代の港湾設備
江戸時代、「水野勝成」を始め福山藩のお殿様たちは「鞆の浦」に奉行所や遠見番所(沖を通る船を見張る役所)を建てて、港の収益を確保するとともに軍事上の拠点として整備させました。
「鞆の浦」には全国で唯一、この時代の港湾施設である「常夜燈」、「雁木(がんぎ)」、「波止場」、「焚場(たでば)」、「船番所(ふなばんしょ)」の全てが残されています。

【常夜灯】(じょうやとう)
常夜燈とは一晩中つけておく明かりのこと。
港町などには灯台の役目をした大型の常夜灯が設置されている。 昔はろうそくや菜種油を燃やして火をつけていた。
【雁木】(がんぎ)
港の船着場における階段のような荷揚げ施設のことです。
潮の満ち干や河川の増水など水面が上下しても、船の大小で高さが変化しても、「雁木」に渡り板を架けて、簡単に昇降や荷役ができました。


【波止場】(はとば)
『波止(はと)』とは、台風などの強風や高波から船を守るために海中に設置された防波堤のこと。鞆の浦には江戸時代に造られた国内最大級の石積みの波止が現存してます。
船が接岸できるので、小舟に荷物を積み替えずに済みます。
【焚場】(たてば)
木造船は,フジツボやカキなどの貝類や船虫から船体を守るため,船底を焼いて乾燥させる必要があります。これを,「たでる」といい,そのたでる場所を「焚場(たてば)」と呼びました。
また,焚場は,長い航海によって痛んだ船体を修理する場所でもありました。

【船番所】(ふなばんしょ)
港に出入りする船を取り締まり、また船の出入りの安全を監視する役所(今の港湾局)のこと。現在の建物は昭和30年頃に建て替えられたものですが、その下の石垣は江戸時代からのものが使われています。
(現在はカフェになっています)

6.なぜ鞆の浦には、こんなに古い物があるのか
これほどに発展した「鞆の浦」ですが、江戸時代の半ば以降には衰え始めます。それは航海術や技術革新により、「鞆の浦」を素通りすることができるようになったからです。
それまでの航海術は「地のり」といって、陸地の近くを、山や大きな木を目印にして現在地を知り、船を操作していました。当然、目印が見えない夜は航海できません。
ところが、江戸中期には「沖のり」という、星や方位磁石を使った航海法が取り入れられ、夜でも進むことが可能になりました。
さらに以前からの「筵帆」(むしろほ)にかわって、丈夫で風をよく受ける木綿帆(もめんほ)が使われるようになり、船の推進力が高くなって、逆潮(さかしお)でも航行することができるようになりました。
このため、「鞆の浦」に停泊する船が激減したのです。
屋敷の天井裏に龍馬が!?『桝屋清右衛門宅』

それでも、風待ちなどでかなりの数の船が「鞆の浦」を使っていました。
坂本竜馬海援隊の「いろは丸」が紀州藩の大型蒸気船「明光丸」と衝突沈没したとき、損害賠償の交渉は「鞆の浦」で行われました。
【いろは丸展示館】 鞆の沖に沈んでいる「いろは丸」の足跡をたどるために作られた資料館です。
江戸期に建てられた蔵をそのまま利用しています。その他の古い建物も江戸末期以降のものがほとんどです。
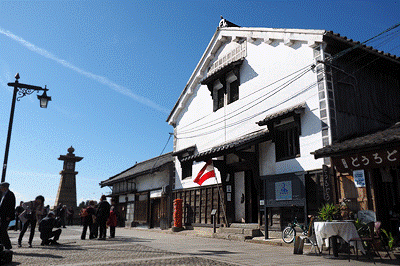
鞆の浦の繁栄にとどめを刺したのは、明治になって敷設された鉄道と戦後の自動車の普及(モータリゼーション)でした。日本全体の交通が、昔からの水運から陸上交通に切りかわりました。

「鞆の浦」は鉄道や国道から遠く、陸上交通の恵みを受けることができません。繁盛していた遊郭や商店、造船所、神社仏閣はさびれ、建物だけが残され、「鞆の浦」はただの寂れた漁村になろうとしていました。
ところが平成17年以後、福山市役所と地元のタイアップにより紹介動画の作成や,テレビ、ホームページ,雑誌,SNSなど,様々な情報発信を行い、「鞆の浦」は、古き良き日本文化の遺跡として、貴重な観光資源になっていったのです。
世の中、何が幸いするか、分かりませんね-
では、よいご旅行を!

コメントを残す